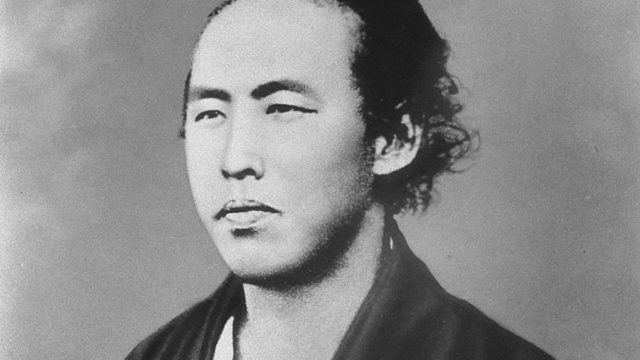織田信長〜勝頼と名乗る武田の甲斐もなくいくさに負けて信濃なければ〜意味と解釈
〈原文〉
勝頼と名乗る武田の甲斐もなくいくさに負けて信濃なければ
〈現代語訳〉
勝つという名がつく勝頼よ、戦いをした甲斐もなく戦に負け、領地だった甲斐国も信濃国もなくなって格好悪いものだ。
概要

戦国武将の織田信長が詠んだ和歌のなかに、武田家滅亡に際し創作され、掛詞をふんだんに使った、さながらラップバトルのような歌があります。
その和歌が、「勝頼と名乗る武田の甲斐もなくいくさに負けて信濃なければ」です。
信長は、長篠の戦いの7年後、天正10年(1582年)に武田家を滅亡させますが、この和歌は、大名家として滅びる武田家最後の武将、武田勝頼の首実検のときに詠んだ歌とされます。
和歌はざっくりと現代語訳すれば、「武田勝頼よ、「勝」と名乗っていながら、戦った甲斐もなく負け、領地の甲斐国も信濃国もなくした。なんと格好悪い(「信濃なく」と「品のなく」を掛ける)ことだ」といった意味になります。
首実検というのは、討ち取った首が確かにその者の首か、大将が確認する作業のことを差し、その首実験の際に詠んだということは、勝頼の首に向かって歌ったということなのでしょうか。
 月岡芳年『真柴久吉武智主従之首実検之図』 慶応2年(1866年)
月岡芳年『真柴久吉武智主従之首実検之図』 慶応2年(1866年)
勝頼の首実検の際、信長は様々に罵り、杖でつき、足で蹴った、というエピソードも残っています。
勝頼の首を滝川が士滝川荘左衛門という使番に持たせて、信長に見せ思せば、さまゝに罵りて、杖にて二つつきて後、足にて蹴られけり。
よほどの憎しみがあったのか、この和歌も、そのときに詠まれたとすれば、信長の高笑いでも聞こえてきそうな光景です。
ただ、織田信長はそれほど和歌を詠むことはなく(信長は和歌よりも茶道具などに興味を持った)、この作品も、後世の誰かが信長の逸話をもとに作ったという説もあるようです。